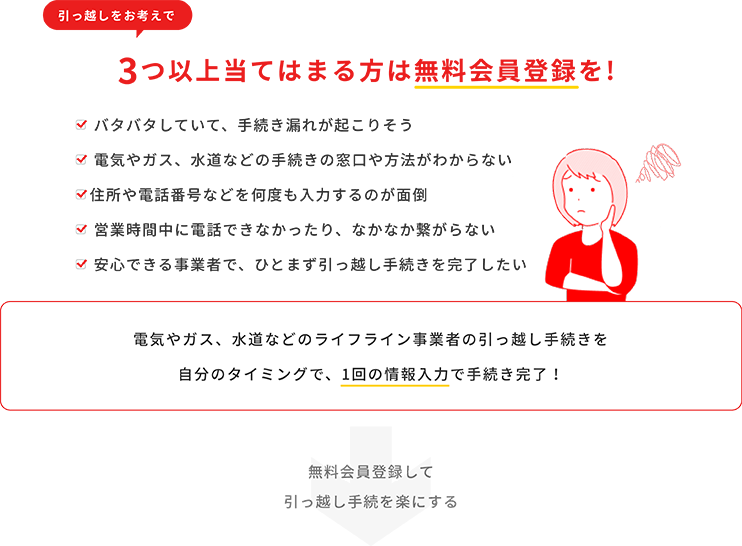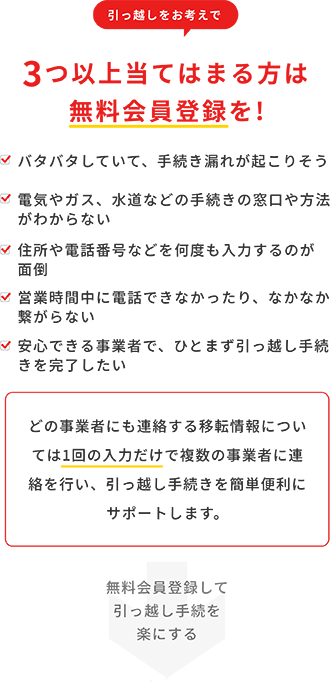郵便局の転居届の提出方法は3つ!必要書類、手続き方法から延長方法まで解説
引っ越しなどで住所が変わった場合、旧住所に届く郵便物は、郵便物の転居・転送サービスを利用することで新住所に届けられます。これは、旧住所に届く郵便物を新住所に1年間無料で転送してくれるサービスです。郵便物の転送を希望する場合には、引っ越し日までに郵便局に転居届を提出し、転送手続きを済ませましょう。
ここでは、郵便局への転居届の提出方法や必要書類などについて解説します。いつからいつまで手続きが行えるのか、転送期間の延長方法、サービスの注意点なども紹介しますので、ぜひご確認ください。
この記事の目次
◆引っ越し時のNHKの住所変更手続き方法を解説!解約の対象は?受信料は?
◆引っ越したら会社に報告する?届け出が必要な理由は?住所変更の報告タイミングと伝え方を解説
◆引っ越しの荷造り完全ガイド!効率よくすすめるコツ、用意する物から手順まで解説
郵便物の転居・転送サービスとは?
郵便物の転送サービスとは、手紙・はがき・ゆうパックなど、引っ越し後に旧住所宛に届く郵便物を、新住所へ無料で転送するサービスです。転送期間は届出のあった日から1年間で、サービス終了後の郵便物は差出人へ返還されます。
サービスの概要、利用のメリットや転送期間について詳しく見ていきましょう。
引っ越し先に郵便物を1年間無料で転送してくれるサービス
郵便物の転送サービスを利用することで、手紙はもちろん、引っ越し前後に購入した小物や雑貨、生命保険などの住所変更書類、クレジットカードの利用明細などが旧住所に郵送されることを防げます。
重要な書類が旧住所に送られるリスクを回避するためにも、引っ越しの際には必ず郵便物転送の手続きをしておきましょう。
注意点は、転送サービスの対象となるのは、日本郵便が取り扱う手紙・荷物のみということです。民間の宅配サービスに関しては、別途住所変更の手続きや差出人への新住所の通知が必要です。
なお、郵便物の転送サービスは無料で利用でき、転送期間は転居届を提出した日から1年間です。
郵便物の転送サービスは更新手続きをすることで期間を1年延長できます。延長手続きについては後の「郵便物の転送サービスの延長方法」で詳しく解説します。
郵便転送用の「転居届」を提出して申し込む
郵便物の転送サービスは、「転居届」を郵便局窓口・ポスト投函・インターネット(e転居)で提出して申し込みすることで、無料で利用できます。
なお、このとき提出する「転居届」は、郵便局がフォーマットを作成している転送用のものです。市町村区役所など行政に提出する転居届とは異なるため、提出する書類を間違えないようご注意ください。
転送用の転居届の用紙は全国の事業所に設置してあります。窓口での直接提出やポスト投函を行う際は郵便局で転居届を入手しましょう。
インターネットでの手続きは、「e転居」のサイトから行えます。直接郵便局に行く時間がない方は、「e転居」サービスを用いて郵便物の転送サービスの利用手続きを行いましょう。
詳細な手続き手順については、「郵便局への転居届提出方法は3つ!」の項目で解説します。
単身赴任や進学で1人のみの転居の際も利用可能
郵便局の転送サービスは、家族全員の引っ越しではなく、1人だけ引っ越しをする場合にも利用可能です。例えば、「単身赴任や進学で家族は旧住所に残り、自分だけ引っ越しをする」というケースが当てはまります。
転居届の「転居者氏名」に、新住所に引っ越しする人の名前だけ記載することで、該当者のみ郵便物の転送サービスを利用できます。ほかにも、長期入院など自宅で郵便物を受け取れない場合、病院に郵便物を転送してもらうことも可能です。
なお、引っ越し前は郵便局の転送手続き以外にも、転出届・転入(転居)届提出、電気・ガス・水道などさまざまなライフラインの住所変更手続きが必要です。引越れんらく帳なら、転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約、電気・ガス・水道などのライフラインの使用停止・開始、NHKの住所変更などをオンラインで手続きできます。複数の手続きを一括で申請できるほか、手続き漏れ防止のアラート機能も提供しています。引っ越しの際は、ぜひ「e転居」と併せて引越れんらく帳をご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

郵便局への転居届の提出に必要なもの一覧
郵便局への転居届の提出に必要なものは、手続きの種類ごとにまとめると以下の通りです。
| 手続きの種類 | 必要書類 |
| 郵便局窓口での手続き | ・転居届用紙 ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど) ・旧住所に住んでいたことが分かる書類 ※法人・団体等の転居手続きをする場合は、社員証・各種健康保険証など、届出人と会社・団体との関係が分かるもの |
| 郵便ポストへ投函 | ・転居届用紙 ・本人確認書類の写し (運転免許証、各種健康保険証、運転経歴証明書、在留カード、マイナンバーカード、特別永住者証明書のうちいずれか) |
| インターネット(e転居)で手続き | ・顔写真つき本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カードのうちいずれか) |
郵便局への転居届提出方法は3つ!各手順を解説
前述のとおり、郵便局への転居届提出方法は
の3種類の手段があります。ここからは、それぞれの手続き手順を解説していきます。
郵便局の窓口で手続き
まず、郵便局の窓口で転居届の用紙を入手し、必要事項を記入します。
転居届の記入が完了したら、運転免許証・各種健康保険証などの本人確認書類と、旧住所が確認できる書類と一緒に、最寄りの郵便局の窓口に提出しましょう。
運転免許証に旧住所が記載されている場合は、本人確認書類と旧住所の確認書類を兼ねることができます。
法人・団体等の転居の手続きをする場合は、転居届用紙と、社員証・各種健康保険証など、届出人と会社・団体との関係が分かるものを窓口に提出する必要があります。転居届は、「届人指名印」欄に、代表者の氏名の記入および押印したものを持参してください。
転居届を郵便ポストへ投函
転居届用紙に必要事項を記入し、本人確認書類の写しと共に付属の専用封筒に入れて、切手を貼らずにポストに投函します。
本人確認書類の写しは、以下の内いずれか1つを用意しましょう。
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 運転経歴証明書
- 在留カード
- マイナンバーカード
- 特別永住者証明書
インターネット(e転居)で提出
「e転居」は、携帯電話やスマートフォンから郵便物の転送を申し込めるサービスです。
e転居の利用には日本郵政グループが提供するサービスをe転居一つでもっと便利にご利用いただけるようになっております。また、eKYCを導入したことによって簡単に本人確認が可能となり、以前は行っていた転居受付確認センターへの電話やマイナポータルAPのインストールの必要がなくなりました。これらに加えまして、2025年2月にリリースされた「郵便局アプリ」からe転居の手続きを行うことも可能になっています。
郵便局への転居届提出と併せて、電気・水道・ガスなどライフラインの手続きの準備も忘れずに進めましょう。「引越れんらく帳」を利用すれば、一度の情報入力だけで、インターネット上で上記ライフラインの手続きを一括で行えます。作業量を大幅に軽減できますので、仕事が忙しく引っ越し作業に時間が取れない方は、ぜひ「引越れんらく帳」を利用してください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

郵便物の転送サービスの手続きはいつまでにすればいい?
郵便物の転送サービスの手続きは、引っ越しが決まったらなるべく早い段階で手続きを完了させましょう。土日や祝日を含む場合には、余裕をもって引っ越しの2週間前までには転居届を提出することをおすすめします。
なぜなら、郵便物の転送サービスは、転居届を提出したらすぐに開始されるわけではないからです。旧住所宛の郵便物が新しい住所に転送されるまで、転居届提出から3~7営業日を要します。そのため、引っ越しギリギリに手続きを行うと、引っ越し完了後も旧居に荷物が届いてしまう可能性がありますので注意しましょう。
なお、転居届用紙には、新住所への転送を始める日付を記入する「転送開始希望日」の欄があります。転居開始希望日は、入居開始日以降を指定しましょう。希望日を具体的に指定することで、郵便物の行き違いや転居前の転送を防げます。引っ越しにかかる日数を計算しながら、適切な日時を記入しましょう。
転居届の受付状況は、郵便局のホームページにある「転居届受付状況確認サービス」で24時間確認できます。受付状況の確認には、転居届申請の受付完了時に案内される、10桁の「転居届受付番号」を使用します。受付状況が確認できるのは、転居届の提出から1年間です(ゆうIDログインのみの場合は30日間)。
「転居届受付番号」の確認方法は、以下の通り申し込みの方法ごとに異なります。
- e転居で申し込んだ場合:受付完了時に届く受付完了メールに記載
- 窓口または郵送で申し込んだ場合:お客様控え「記入要領」の欄に記載
引っ越し直前にあわてないためにも、各種手続きは早めに済ませるようにしましょう。簡略化・時短には、ライフラインの手続きをオンラインで一括完了できるサービス「引越れんらく帳」が役立ちますので、ぜひチェックしてみてください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

郵便物の転送サービスの延長方法
郵便転送サービスの期間は1年間ですが、更新手続きを行うことで、さらに1年間転送期間を延長できます。申請方法は、転居届の提出と同様に「郵便局窓口で手続き」「転居届をポスト投函」「インターネット(e転居)で提出」の3つです。延長の手続きも完了まで1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって行いましょう。
なお、転送サービスの利用期間が過ぎた後でも、延長手続きは可能です。ただし、延長手続きが完了するまでの間は旧住所に荷物が送られてしまいますので、ご注意ください。
また、前述の通り民間の宅配業者が扱う荷物は転送されないため、なるべく早い時期に差出人に新しい住所を通知することをおすすめします。その他、「転送不要」と記載された郵便物も転送されないのでご注意ください。
郵便物の転送サービスの延長回数に制限はある?
郵便転送サービスは、回数の制限なく期間の延長ができます。しかし、回数制限がないといっても、1年ごとに延長手続きを行うことは非常に面倒です。
転送期間中の早い段階で、新住所への住所変更手続きを済ませておきましょう。
郵便物の転送サービスを利用するときの注意点
郵便転送サービスを利用する際の注意点をまとめました。手続き前に一度ご確認ください。
転送開始希望日は入居開始日以降にする
転居届には、転送開始希望日を記入する欄があります。転送手続きは、申し込みから完了まで1週間程度かかります。郵便物の行き違い等のトラブルを防ぐためにも、転送開始希望日には、入居開始日以降の日付を必ず記入しましょう。転送開始希望日が入居開始日より前になると、前の居住者がいる住所や、入居者がいない住所に郵便物が転送されてしまうので注意してください。
「転送不要」・「転送不可」の郵便物はサービスの対象外
郵便物の転送サービスを利用すれば、どんな郵便物でも転送が可能なわけではありません。「転送不要」・「転送不可」と記載がある郵便物は、転送サービスの対象外になるため、注意しましょう。
例えば、クレジットカードやキャッシュカードが入った書類、保険や税金などの納付書類、パスポートなどは防犯の観点から転送が不可となっています。「転送不要」・「転送不可」の郵便物は、通常であれば簡易書留などで送られてきます。引っ越し後に届かない書類がある場合には、差出人に直接問い合わせをし、住所変更等の手続きを行いましょう。
郵便局以外の宅配業者が扱う荷物は転送されない
郵便物の転送サービスの対象となるのは手紙やはがき、ゆうパックなど日本郵便が扱う郵便物に限られます。民間の宅配業者が扱っているメール便などの転送については、それぞれの業者ごとに転送を申し込む必要があります。忘れずに手続きしましょう。
転送期間内に再度住所を変更する際は手続きが必要
郵便物の転送サービスは、転送の手続きを行うと1年以内の停止・解除ができません。転送の手続きから1年以内に再度引っ越しをし、転送先の住所を変更したい場合は、新たに転居届を出し直して再度手続きを行う必要があります。
サービスの期間が過ぎると郵便物は差出人に返却される
郵便物の転送サービスの転送期間は、転居届を提出した日から1年間です。期間終了後は、荷物の差出人に返却されます。延長手続きをしないと、郵便物が手元に届かなくなるので注意してください。
転送期間終了後も延長手続きは可能ですが、手続きの完了までは1週間程度時間がかかってしまいます。荷物が届かない期間が生じる恐れがあるので、延長手続きは転送期間中に余裕をもって行うことをおすすめします。
郵便物の転居・転送サービスについてのよくある質問
郵便物の転居・転送サービスについて、よくある質問は、次のようなものがあります。
郵便物の転送は本人以外でもできますか?
本人以外でも郵便物の転送手続きは可能です。 また、世帯の人以外が代理人として申請することが可能です。転居・転送手続きをする際は、誰が転居するのか、誰が手続きをするのかをはっきりさせることが大切です。また、委任状が必要な場合があるため、事前に必要書類を確認し、準備するようにしましょう。携帯電話やスマートフォンから「e転居」を利用すると、比較的簡単に手続きが可能です。
住民票を移さずに郵便物を転送できますか?
住民票を移していない場合も、郵便局に転居届を出すことは可能です。手続き先が役所とは異なるため、住民票を移さない場合でも転送サービスは利用できます。ただし、転送サービスは、一時的なもので、期限は1年間となっています。利用期間に注意しましょう。
家族のうち1人が引っ越しをする場合、転送できますか?
転送できます。 転居届を提出する際、「転居者氏名」欄に転居する方の氏名をご記入ください。郵便局の窓口、またはインターネットサービス「e転居」で手続き可能です。ちなみに「e転居」を利用すると、最大6人までの家族の転送依頼をまとめて行えます。e転居の申請者は手続きにあたり本人確認が必要ですが、世帯主である必要はありません。
郵便転送とあわせて、引越れんらく帳でライフラインの住所変更を!
引っ越しの際には、郵便物の転送サービスの手続きが欠かせません。最寄りの郵便局窓口に転居届を提出するだけで簡単に手続きができるため、時間があるときに余裕をもって進めましょう。
引っ越しは荷造りや手続きなど、たくさんやるべきことがあります。リストアップし、効率よく手続きを済ませるのがおすすめ。これから引越しを控えている人は次の「引っ越しやることリスト」を利用しながら、スケジュールの管理に役立ててください。チェックリストをPDFとエクセルでダウンロードできます。
また、引っ越しでは郵便物をはじめ、電気・ガス・水道などのライフラインの住所変更も必要です。
手間のかかる引っ越し手続きを効率よく進めたいという方には、「引越れんらく帳」という無料Webサービスの利用がおすすめです。ライフラインの手続きだけでなく、転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約、ソフトバンク光、ドコモ光などのインターネット事業者やNHKの住所変更など、面倒な引っ越し手続きをインターネットでまとめて完結させられます。
「引越れんらく帳」で住所変更を一気に済ませ、引っ越し準備の負担を軽くしてみてはいかがでしょうか。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

◆引っ越し時のNHKの住所変更手続き方法を解説!解約の対象は?受信料は?
◆引っ越したら会社に報告する?届け出が必要な理由は?住所変更の報告タイミングと伝え方を解説
◆引っ越しの荷造り完全ガイド!効率よくすすめるコツ、用意する物から手順まで解説