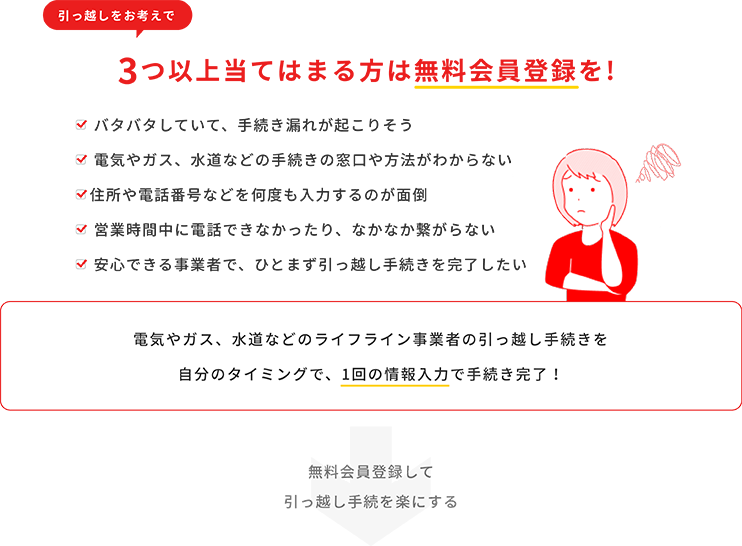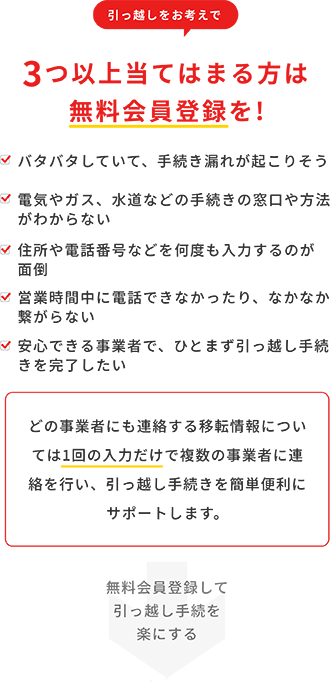引っ越し時に役所で住所変更手続きが必要なもの一覧!タイミングや手順、必要書類まとめ
引っ越しに伴う役所手続きは種類が多く、何をいつやればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。提出期限がある手続きの場合、期限を過ぎると過料が科される可能性もあるため注意が必要です。本記事では、引っ越し時に役所で行う手続きや順番、期限、必要書類について解説します。引っ越し予定の方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次
◆引っ越し手続きのやることチェックリスト!タイミングや必要書類などまとめて解説
◆郵便局の転居届の提出方法と必要なものは?引っ越し先への転送・延長方法を解説
引っ越し時役所でやることリスト
引っ越し時は、役所でさまざまな手続きをする必要があります。下の表は、引っ越しの際に役所で行う手続きの種類やタイミングをまとめたものです。このリストを参考にして、手続きを漏れなく進めましょう。
<必ず行う手続き>
| 手続きの種類 | 手続きのタイミング |
| 転出届の提出 | 引っ越し14日前から引っ越し当日 |
| 転居届あるいは転入届の提出 | 引っ越し日から14日以内 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 引っ越し日から14日以内 ※転入届提出後90日以内に手続き完了しないとマイナンバーカードが失効する |
<該当する場合に必要な手続き>
| 手続きの種類 | 手続きのタイミング |
| 印鑑登録の住所変更 | 規定なし(引っ越し後なるべく早く行う) |
| 国民健康保険の住所変更 | 引っ越しから14日以内 |
| 国民年金の住所変更 | 引っ越しから14日以内 |
| 介護保険の住所変更 | 引っ越しから14日以内 |
| 犬の登録 | 規定なし(引っ越し後なるべく早く行う) |
<妊娠中または子どもがいる場合に必要な手続き>
| 手続きの種類 | 手続きのタイミング |
| 健康診査費用補助券の再発行 | 自治体により異なる |
| 児童手当の住所変更 | 転出予定日から15日までに完了するのが望ましい |
| 保育園や幼稚園の転園手続き | 転園先が決まり次第すぐ |
| 公立の小中学校の転校手続き | 転校先が決まり次第すぐ |
<給付金の対象者が役所で行う手続き>
| 手続きの種類 | 手続きのタイミング |
| 結婚新生活支援事業の手続き | 自治体により異なる |
| 住宅確保給付金の手続き | 離職廃業から2年以内 もしくは、給与を得る機会が離職廃業と同程度まで減少している場合 |
なお、引越れんらく帳を利用すれば転出届の提出と転入(転居)届提出のための来庁予約がオンライン上で可能です。転出届提出のために旧居の役所に行く手間を省け、新居で必要になる転入(転出)届提出時の役所への来庁予約が事前に行え、電気・ガス・水道などライフラインの使用停止・開始手続きも合わせて行うことができます。効率よく引っ越し手続きを済ませたい方は、ぜひ引越れんらく帳をご利用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

役所で行う手続きの順番・タイミング
引っ越しに伴う役所での手続き期間の多くは、引っ越し日の前後14日間に設定されています。直前に慌てないように、余裕をもって手続きをしましょう。
手続きは、引っ越し前の旧居と引っ越し後の新居での手続きとで分けて考えるとわかりやすいです。引っ越し前は、旧居の役所で「転出届の提出」「印鑑登録の廃止申請」「国民健康保険の資格喪失手続き」などを行います。引っ越し後は、新居の役所で「転入届の提出」「印鑑登録証の発行」「国民健康保険の加入手続き」「マイナンバーカードの住所変更」などを行います。
| 【引っ越し前】 旧居の役所で行う手続き |
・転出届の提出 ・国民健康保険の住所変更または資格喪失手続き ・印鑑登録の廃止 ・児童手当の住所変更または受給事由消滅届の手続き ・介護保険被保険者の住所変更または返納 ・子どもの転園・転校に関する手続き |
| 【引っ越し後】 新居の役所で行う手続き |
・転居届または転入届の提出 ・マイナンバーの住所変更 ・印鑑登録の手続き ・国民健康保険の加入手続き ・国民年金の住所変更 ・児童手当の認定申請 ・福祉手当、医療制度の住所変更 ・パスポートの住所変更(本籍地を変更した場合) |
土日対応している役所もある
自治体によっては、土日でも一部の窓口を利用できる場合があります。旧居の役所と新居の役所のホームページを見て、土日対応の有無を確認しましょう。オンラインや郵送でできる手続きもあり、一部の届出についてはマイナポータルからの手続きも可能ですので、自治体窓口に問い合わせください。
代理人が手続き可能な場合もある
引っ越し時に役所で行う手続きは、本人ができない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が手続きをする際は、委任状や身元確認書類が必要になります。
代理人による提出が可能な手続きは以下の通りです。
- 転居届
- 転出届、転入届
- マイナンバーカード
- 印鑑登録
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険
- 健康診査費用補助券の再発行
- 結婚新生活支援事業の手続き
- 住宅確保給付金の手続き・児童手当の住所変更
- 保育園や幼稚園の転園手続き
- 公立の小中学校の転校手続き
※詳細は各自治体に確認してください
なお、ペットの登録事項変更は、原則として代理人による手続きができません。
また、マイナンバーカードの代理人(任意代理人)による手続きについては、代理人の手続き申請を受付後、市役所から申請者あてに郵送する「照会書兼回答書」の持参を命じている自治体が多いです。よって、基本的に即日で手続きを完了することはできませんので注意しましょう。
新居の住民票の写しを早めに取得する
運転免許証の住所変更や銀行口座の登録変更、学校の転校手続きには、新しい住所が記載された住民票の写しが必要です。
引っ越し後、転入届の提出やマイナンバーカードの住所変更などが完了したら、住民票を数枚取得しておきましょう。
また、住民票を移さないことには、次のようなデメリットがあります。
- 選挙の投票が旧居の選挙区でしか行えない
- 運転免許の更新手続きが旧居の地域でしかできない
- 新居がある地域の役所で公的な証明書を取得できない
- 本人確認の郵便を一部受け取れない場合がある
- 新居と運転免許証など本人確認書類の住所が異なる
- 図書館など新居がある地域の公共施設が利用できなかったり、利用が制限されたりする
新住居がある自治体の行政サービスを利用できず、さまざまな不便が想定されます。また、住民票の移行を忘れたままにしておくと、5万円以下の過料を科されます。詳しくは 「引っ越し時に住所変更しないとどうなる?住民票の異動はいつまで?リスクと手続き方法を解説」をご覧ください。
引っ越し後は早めに住民票を移しましょう。
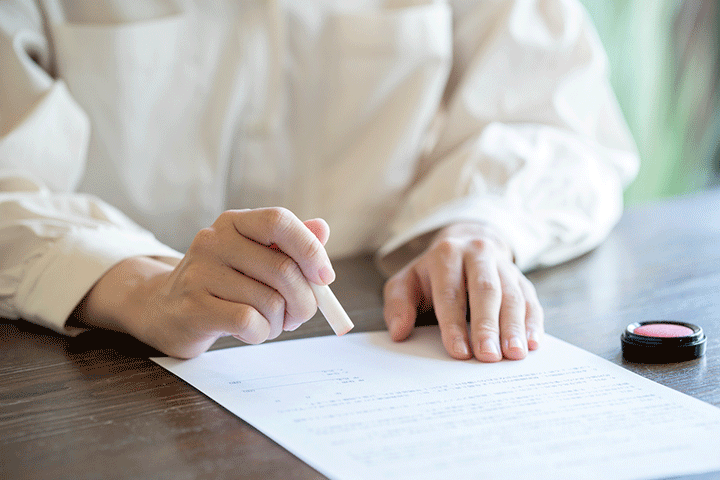
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越し先が決まり次第すぐに役所で行う手続き
引っ越しが決まり次第すぐに役所で行ったほうがよいのは、子どもの転園・転校手続きです。引っ越し先の保育園、幼稚園、小中学校に空きがなく、すぐに転園・転校先が決まらないこともあるからです。手続きも自治体によって異なりますので、引っ越し先の自治体に早めに連絡し、手続きを進めていきましょう。
保育園や幼稚園の転園手続き
保育園や幼稚園に通っている子どもがいる場合は、保育園や幼稚園の転園手続きを行います。手続きの前に、引っ越し先で希望する保育園や幼稚園に空きがあるかどうかも確認しておきましょう。
別の保育園や幼稚園に転園する場合は、退園届を提出し、新規入園と同じ手続きを行います。引っ越し後も同じ保育園や幼稚園に通う場合は、家庭(世帯)状況等変更届などを提出し、住所変更手続きを行ってください。
手続きの内容は保育園や幼稚園・自治体によって大きく異なるため、事前に確認しましょう。
■転園手続き
| 手続きの対象者 | 保育園や幼稚園に通っている子どものいる家庭 |
| 期限 | 転園先が決まり次第すぐ |
| 手続き場所 | 市区町村役所 |
| 持ち物 | ・入園願書 ・住民票 ・在園証明書 |
保育園や幼稚園の転園手続きについては、以下の記事も参考にしてください。
◆引っ越しで保育園を転園する際の手続き方法と転園時の確認事項
◆幼稚園を転園する方法とは?引っ越しで必要な手続きや注意点を解説
小中学校の転校手続き
小中学生の子どもがいる家庭は、転校手続きをしなくてはなりません。
同一市区町村内に引っ越しをして、公立の小・中学校に通う場合、在学中の学校に転校の旨を伝え、「在学証明書」および「教科書給与証明書」を発行してもらいましょう。その後、役所の住民異動手続きにて、「転入学通知書」を受け取ります。
在学証明書と教科書給与証明書、転入学通知書の3点を新しい学校に提出すれば完了です。
他の市区町村に引越しをして、転校する場合も同じ流れです。
私立の場合、まず転校を希望する学校に問い合わせて編入可能かどうかを確認してください。編入条件を事前に調べたり、学校見学をしたりすることがおすすめです。その後、編入学試験に合格し、学校に指定された必要書類を提出すると転校できます。
■小中学校の転校手続き
| 手続きの対象者 | 小中学校に通っている子どものいる家庭 |
| 期限 | 転校先が決まり次第すぐ |
| 手続き場所 | 市区町村役所 |
| 持ち物 | ・新規入学に必要な持ち物 ・在学証明書 ・教科書用図書給与証明書 ・転入学通知書 |
小中学校の転校手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
◆小学校を転校する際の手続きと住所変更に伴い準備すべきことを解説!
◆中学校の転校手続きの流れとは?転入先を決める際の注意点や準備するものを解説
また高校の転校手続きでは、欠員確認や入学試験が必要なため、新居の自治体の教育委員会に連絡が必要です。高校の転校手続きについては「高校の転校手続きの流れ│転入先を決める際の条件・注意点と準備するもの」をご確認ください。
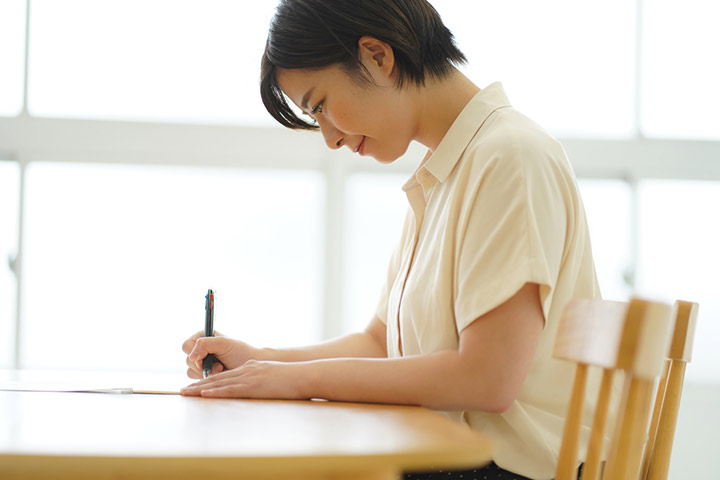
引っ越し2週間前~当日に役所で行う手続き
引っ越しの2週間前から当日にかけては、以下の手続きをしましょう。
- 転出届の提出
- 国民健康保険の資格喪失手続き
- 印鑑登録の抹消
- 介護保険の住所変更
- 犬(ペットの登録)
転出届の提出と国民健康保険の資格喪失手続きは、他の市区町村に引っ越す場合に必要です。引っ越し直前はバタバタしますので、余裕をもって手続きを始めましょう。 ここからは、各手続きの詳細について解説します。
転出届の提出【他の市区町村へ引っ越し】
他の市区町村へ引っ越しする場合、旧居の役所に転出届を提出します。転出届の提出期限は引っ越し14日前から引っ越し当日までです。
また新居の役所で転入届を提出する際「転出証明書」が必要です。転出届が完了していないと転入届も提出できないため、早めに対応しましょう。
また、マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルまたは引越れんらく帳からオンラインで転出届提出や転入(転居)届提出のための来庁予約が可能です。 マイナポータルまたは引越れんらく帳から「転出届」を旧居の区市町村に申請すると「転出証明書」の交付無しで新居の区市町村で転入(転居)手続きができます。転出届のオンライン提出方法は「引越しワンストップサービスのやり方を解説!転出届をマイナポータル・引越れんらく帳からオンライン提出」で詳しく解説しています。
引越れんらく帳なら、転出届提出、転入(転居)届提出のための来庁予約だけでなく電気・ガス・水道などのライフラインやインターネット、NHKの引っ越し手続きもできます。できるだけかんたんに引っ越し手続きを済ませたい方は、ぜひ引越れんらく帳をご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

■転出届の手続き
| 手続きの対象者 | 他市区町村へ引っ越しする人 |
| 期限 | 引っ越し14日前から引っ越し当日まで |
| 手続き場所 | 市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・印鑑 ・印鑑登録証(登録している場合) ・国民健康保険証(国民健康保険に加入する自営業者など) ・高齢者医療受給者証(70歳~74歳の方) ・乳幼児医療証(乳幼児がいる対象) |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・代理人の場合の持ち物 ・本人が申請する場合の持ち物一式 ・代理人の本人確認書類 ・委任状 ・代理人の印鑑 |
転出届の手続きは「転出届の提出はいつからいつまで?引っ越し後でも大丈夫?」の記事でも詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
国民健康保険の資格喪失手続き【他の市区町村へ引っ越し】
国民健康保険加入者が他の市区町村へ引っ越しする場合、引っ越し前に資格喪失手続きが必要です。代理人による申請手続きも可能です。
必要なものは、健康保険証、印鑑、マイナンバーが確認できるものです。手続き期限は、引っ越し日(国民健康保険の資格喪失日)から14日以内です。引っ越し後でも手続きできますが、何度も来庁する手間を省くために転出届提出と同時に国民健康保険の資格喪失手続きを行うのがおすすめです。
手続きを忘れると、旧居に本来必要のない保険料が請求されてしまうこともありますので、忘れずに行いましょう。
■国民健康保険資格喪失手続き【他の市区町村へ引っ越し】
| 手続きの対象者 | 国民健康保険の第1号被保険者 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・健康保険証 ・印鑑 ・マイナンバーが確認できるもの |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の健康保険証 ・代理人の本人確認書類 ・委任状 |
印鑑登録の抹消
他の市区町村に引っ越す場合には、役所に登録した印鑑(実印)の廃止・登録手続きが必要です。同じ市区町村内の引っ越しの場合は転居届提出をもって印鑑登録の住所も変更されますが、政令指定都市内で別の区へ引っ越しする場合・東京23区内での引っ越しの場合は、廃止手続きが必要な可能性があるため自治体のホームページで確認しておきましょう。
手続きは、引っ越し前に旧居の役所で印鑑登録廃止申請を行い、引っ越し後に新居を管轄する役所であらためて印鑑登録を行います。不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておきましょう。
印鑑登録の廃止手続きは、転出届の提出と同時に行うのがおすすめです。また、印鑑登録は代理人が申請することも可能です。
自治体によっては、転出届の提出と同時に登録廃止が抹消される場合もあります。その際は、印鑑登録証を返却するだけで構いません。手続き方法の詳細については、各自治体のルールに従うようにしましょう。
■印鑑登録の抹消手続き
| 手続きの対象者 | 他の市区町村に引っ越す人 (同じ市区町村でも例外あり) |
| 期限 | 規定なし |
| 手続き場所 | 旧居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・印鑑登録証 ・本人確認書類 |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・印鑑登録証 ・代理人の本人確認書類 ・委任状 ・本人(委任者)の本人確認書類 |
介護保険の住所変更
自分自身や家族が介護保険に加入している場合は、新居の住所に関係なく住所変更手続きを行う必要があります。代理人による申請も可能です。
ただし、手続きの方法は新居の住所によって少し異なります。新居が同じ市区町村の場合、転居届提出と一緒に介護保険の住所変更を申請し、新しい介護保険被保険者証の交付を受けてください。転居前まで利用していたサービスを継続できます。
他の市区町村に引っ越す場合、まず旧居の役所に「介護保険被保険者証」を返納し、資格喪失手続きを行います。それに伴い新たな「介護保険受給資格証」が交付されますので、新居の役所で介護保険加入手続きを行ってください。
手続きの期限や持ち物は市区町村によって異なる場合があるため、事前に自治体のホームページをご確認ください。
■介護保険の住所変更手続き【同じ市区町村内で引っ越し】
| 手続きの対象者 | 介護認定を受け、サービスを利用している人 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・印鑑登録証 ・本人確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の介護保険被保険証 ・本人(委任者)の確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) ・委任状もしくは登記事項証明書 |
■介護保険の住所変更手続き【他の市区町村へ引っ越し】
| 手続きの対象者 | 国民健康保険の第1号被保険者 |
| 期限 | 資格喪失手続き:引っ越し日まで 加入手続き:引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 資格喪失手続き:旧居の市区町村役所 加入手続き:新居の市区町村役所 |
| 【資格喪失】本人が手続きする場合の持ち物 | ・印鑑登録証 ・本人確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) |
| 【資格喪失】代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の介護保険被保険証 ・本人(委任者)の確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) ・委任状もしくは登記事項証明書 |
| 【加入】本人が手続きする場合の持ち物 | ・介護保険受給資格証 ・本人確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) ・印鑑 |
| 【加入】代理人が手続きする場合の持ち物 | ・介護保険受給資格証 ・本人(委任者)の確認書類 (個人番号の確認が必要な場合あり) ・委任状もしくは登記事項証明書 |
介護保険の手続きについては「介護保険の住所変更 手続きの流れは?市内市外への引越しは?パターン別に解説」の記事でも詳しく解説しています。
犬(ペット)の登録
犬、または国の指定動物を飼育されている方は、引っ越しの際に定められた手続きをする必要があります。犬を飼っている方は、狂犬病予防の観点から各市区町村への登録が義務付けられています。市区町村ごとに手続きが異なりますので、事前にチェックしておきましょう。
同じ市区町村内で引っ越す場合は、転居届とともに「登録事項変更届」を提出してください。他の市区町村へ引っ越す場合は、旧居の管轄自治体にて鑑札を発行してもらいます。引っ越し後、新居の役所に鑑札を持参して登録住所の変更手続きを行ってください。
手続きの期限や持ち物は市区町村によって異なる場合があるため、手続き前に市区町村役所のホームページをご確認ください。
なお、猫やハムスターなど小型動物の場合は、住所変更の手続きは不要です。
■犬の登録手続き【同じ市区町村内で引っ越し】
| 手続きの対象者 | 犬を飼育している人 |
| 期限 | 規定なし(できるだけ速やかに) |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 持ち物 | ・登録事項変更届 ・狂犬病予防注射済証 ・印鑑 |
■犬の登録手続き【他の市区町村へ引っ越し】
| 手続きの対象者 | 犬を飼育している人 |
| 期限 | 規定なし(できるだけ速やかに) |
| 手続き場所 | 鑑札の発行:旧居の市区町村役所 登録:新居の市区町村役所 |
| 持ち物 | ・旧住所の自治体で発行された鑑札 ・登録事項変更届 ・狂犬病予防注射済証 ・印鑑 |
■国の指定動物の引っ越し手続き
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種は、特定動物として規制の対象とされています。 特定動物(ワニ、タカなど人に危害を加えるおそれのある国から指定された動物)を飼養している人は、引っ越しの際自治体が定める手続きを行う必要があります。手続き方法については、新居を管轄する都道府県または、政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせてください。
参考:環境省「地方自治体連絡先一覧」
なお、令和2年6月1日より、特定動物を愛玩目的等で新たに飼養することは禁止されているため、対象はそれ以前に許可を得て飼養している人に限られます。
引っ越し当日~2週間後に役所で行う手続き
引っ越し当日から2週間後までに行う手続きをご紹介します。窓口来庁が必要ですので、計画的に手続きを進めましょう。
転居届の提出【同じ市区町村内で引っ越し】
同じ市区町村内で引っ越す場合は、役所に転居届を提出します。引っ越しから14日以内に提出しましょう。期限内に転居届を提出しなかった場合、5万円以下の過料を科される可能性があります。
転居届の申請方法については、「転出届・転入届・転居届に必要な書類は?提出方法と合わせて解説」の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。
■転居届の手続き
| 手続きの対象者 | 同じ市区町村内で引っ越しをした人 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) ・印鑑 ・マイナンバーカード(交付されている方のみ) ・国民健康保険証(国民健康保険に加入する自営業者などのみ) ・高齢者医療受給者証(70歳~74歳の人のみ) ・乳幼児医療証(乳幼児がいる人のみ) |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の本人確認書類 ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードなど) ・委任状 ・国民健康保険証(国民健康保険に加入する自営業者などのみ) ・高齢者医療受給者証(70歳~74歳の人のみ) ・乳幼児医療証(乳幼児がいる人のみ) ・代理人の印鑑 |
引越れんらく帳では、転居届提出の来庁予約がオンラインでできます。あらかじめ来庁予約をしておくことで待ち時間を短縮できるので、忙しい方におすすめです。ライフラインやインターネット、NHKなどの手続きも引越れんらく帳から申請できますので、ぜひご利用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

転入届の提出【他の市区町村へ引っ越し】
他の市区町村へ引っ越す場合、旧居の役所に転出届、新居の役所には転入届を提出します。手続きの期限は引っ越し日から14日以内で、正当な理由なく届け出を怠ると5万円以下の過料が科される恐れがあります。
手続きに必要なものは、転出証明書・本人確認書類・印鑑です。転出証明書は転出届提出時に、旧居の役所で発行されます。紛失しないように保管しておきましょう。
■転入届の手続き
| 手続きの対象者 | 他の市区町村へ引っ越しした人 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・転出証明書 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・印鑑 |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・転出証明書 ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・委任状 ・代理人の印鑑 |
マイナンバーカードを所有していれば、マイナポータルまたは引越れんらく帳からオンラインで転出届提出と転入届提出の来庁予約ができます。
転入手続きについては「転入届は引っ越し前に提出できる?提出はいつからいつまで?」でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

国民健康保険の住所変更【同じ市区町村内で引っ越し】
同じ市区町村内で引っ越す場合も、住所変更手続きをしましょう。手続き期間は、引っ越し日(国民健康保険の資格を喪失した日)から14日以内です。転居届提出と同時に行うと、何度も来庁する手間が省けます。
手続きに必要なものは、保険証や本人確認書類、マイナンバーが確認できるものなどです。国民健康保険の変更手続きを忘れると、健康保険証が利用できないこともありますので、すみやかに手続きしましょう。
■国民健康保険の住所変更手続き【同じ市区町村で引っ越し】
| 手続きの対象者 | 国民健康保険の第1号被保険者 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・健康保険証 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・印鑑 |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の健康保険証 ・代理人の本人確認書類 ・委任状 ・代理人の印鑑 |
国民健康保険の新規加入手続き【他の市区町村へ引っ越し】
他の市区町村へ引っ越す場合には、新居の役所で国民健康保険の新規加入手続きが必要となります。手続き期間は、引っ越し日(国民健康保険の資格を喪失した日)から14日以内です。転入届提出と一緒に国民健康保険の加入手続きもするのがおすすめです。
新規加入手続きに必要なものは、保険証や本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの、転出証明書などです。自治体によっては印鑑も必要な場合もあります。期限内に手続きをしないと保険証が利用できなくなることもありますので、ご注意ください。
■国民健康保険の住所変更手続き【他の市区町村へ引っ越し】
| 手続きの対象者 | 国民健康保険の第1号被保険者 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・健康保険証 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ・転出証明書 ・印鑑 |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・本人(委任者)の健康保険証 ・代理人の本人確認書類 ・転出証明書 ・委任状 ・代理人の印鑑 |
マイナンバーカードの住所変更
マイナンバーカードを持っている場合、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。引っ越し後14日以内に手続きしましょう。転入届の提出後、90日以内に住所変更手続きを行わなかった場合はマイナンバーカードが失効してしまいますので、ご注意ください。
なお、顔写真がついていない「マイナンバー通知カード」は2020年5月に廃止されたため、マイナンバー通知カードの住所変更手続きは不要です。
代理人による手続きもできますが、市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前に新居の市区町村役所のホームページをご確認ください。
■マイナンバーカードの住所変更手続き
| 手続きの対象者 | 引っ越しで住所が変わる人 |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・印鑑 ・マイナンバーカード ・4桁の暗証番号 ・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・代理人の本人確認書類 ・委任状 ・代理人の印鑑 ・本人(委任者)のマイナンバーカード ・本人(委任者)の4桁の暗証番号 |
引っ越しに伴うマイナンバーカードの手続きについては「引っ越し後はマイナンバーカードの変更手続きが必要!手順や期限を解説」もご確認ください。
マイナンバーカードがあるとさまざまな手続きの本人確認書類として使えるほか、社会保障、税金、災害対策に関する行政手続きがスムーズに行えるようになりますので、期限内に手続きを済ませましょう。
国民年金の住所変更
国民年金も新居の役所で住所変更が必要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、住民票を移動させるだけで変更手続きされます。手続きは代理人が行うこともできます。
■国民年金の住所変更手続き
| 手続きの対象者 | 国民年金の第1号被保険者 (マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合) |
| 期限 | 引っ越し日から14日以内 |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・国民年金手帳 ・印鑑 ・本人確認書類 |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・国民年金手帳 ・印鑑 ・本人(委任者)の本人確認書類 ・代理人の本人確認書類 ・委任状 |
児童手当の住所変更
児童手当とは、子育て世帯に支給される助成金のことです。他の市区町村へ引っ越す場合は、児童手当の住所変更が必要です。同じ市区町村内の引っ越しは、転居届を提出のみで、児童手当手続きは不要です。
自治体によって、郵送や電子申請、代理人による手続きを受け付けている場合もあるためご確認ください。
■児童手当の住所変更手続き
| 手続きの対象者 | 他の市区町村に引っ越す 0歳~中学生の子どもがいる世帯 |
| 期限 | 引っ越し日から15日以内 |
| 手続き場所 | 旧居・新居の市区町村役所 |
| 旧居での手続きに必要な持ち物 | ・児童手当受給事由消滅書 ・印鑑 |
| 新居での手続きに必要な持ち物 | ・児童手当認定請求書 ・印鑑 ・本人確認書類 ・普通預金通帳やキャッシュカード ・健康保険証の写し ・課税証明書(所得証明書) |
児童手当の住所変更手続きについては「引越しに伴う児童手当の住所変更手続き方法と必要なものをわかりやすく解説」もご確認ください。
また引っ越しでは、役所関連の手続きに加えて、電気・ガス・水道などのライフラインの手続きも必要です。引越れんらく帳では、転出入の手続きとライフラインの手続きがインターネット上でまとめてできます。引っ越しの手間や時間を節約したい方は、ぜひご利用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

本人や自治体によってタイミングが異なる手続き
該当者のみ必要になる手続きについてもご紹介します。自治体によって手続き方法や期限が異なるので、事前にチェックしておきましょう。
健康診査費用補助券の再発行
健康診査(妊婦検診)の費用補助券とは、母子手帳の交付とともに自治体が発行する補助券で、妊婦検診費用の補助を目的とするものです。「妊婦健康診査費用補助券」「妊産婦健康診査費用補助券」など、自治体によって名称は異なります。妊娠中の方で現住所と他の市区町村へ引っ越しする場合、健康診査費用補助券の再発行が必要です。手続き方法に関しては自治体によって異なるため、各ホームページを事前に確認しておきましょう。
代理人による申請もできますが、自治体によっては、夫や夫婦の父母など代理人の条件があるため注意しましょう。
■健康診査費用補助券の再発行手続き
| 手続きの対象者 | 他の市区町村に引っ越す妊娠中の人 |
| 期限 | 自治体によって異なる |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 本人が手続きする場合の持ち物 | ・母子手帳 ・残りの補助券 ・本人確認書類(個人番号の確認が必要な場合あり) |
| 代理人が手続きする場合の持ち物 | ・母子手帳 ・残りの補助券 ・本人(委任者)の確認書類(個人番号の確認が必要な場合あり) ・本人(委任者)の印鑑 ・委任状 |
母子手帳の住所変更手続きについては「母子手帳の変更手続きは必要?妊婦が引っ越しの際に対応すべきこと」の記事で詳しく解説しています。
結婚新生活支援事業の手続き
「結婚新生活支援事業」は結婚にかかる費用に対して、国が支援を行う事業です。すべての自治体で実施されているわけではないため、新居の市区町村が制度の対象かどうかを事前に確認してください。
主に新居の購入費や引っ越し費用が支援の対象となります。結婚式費用や家具家電の購入費用は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
結婚新生活支援事業には、「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2種類があります。
■結婚新生活支援事業(一般コース)の手続き
| 手続きの対象者 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ、 世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新規に婚姻した世帯 |
| 補助上限額 | 1世帯当たり30万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 期限 | 自治体によって異なる |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 持ち物 | ・補助金交付申請書 ・結婚届受理証明書 ・入籍後の戸籍謄本 ・住民票の写し ・所得証明書 ・新居に関する書類(契約書等) ・振込口座がわかる書類 ・税金滞納が無いことを証明する書類 |
■結婚新生活支援事業(都道府県主導型市町村連携コース)の手続き
| 手続きの対象者 | 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ、 世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新規に婚姻した世帯 |
| 補助上限額 | 夫婦ともに29歳以下:60万円 上記以外:30万円 (いずれも1世帯当たり) |
| 補助率 | 2/3 |
| 期限 | 自治体によって異なる |
| 手続き場所 | 新居の市区町村役所 |
| 持ち物 | ・補助金交付申請書 ・結婚届受理証明書 ・入籍後の戸籍謄本 ・住民票の写し ・所得証明書 ・新居に関する書類(契約書等) ・振込口座がわかる書類 ・税金滞納が無いことを証明する書類 |
結婚新生活支援事業については「新婚世帯は補助金がもらえる?「結婚新生活支援事業」と申請方法を解説」でも解説しています。申請を考えている方は、ぜひご一読ください。
住宅確保給付金の手続き
「住宅確保給付金」は離職や廃業などにより引っ越しせざるを得なくなったとき、引っ越し費用などに支払われる給付金です。支援金額の上限は自治体ごとに定められており、家賃の3か月分の支給を受けられます。
■住宅確保給付金の手続き
| 手続きの対象者 | 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内 もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している人 ※詳細な要件は各自治体のホームページを参照ください |
| 期限 | 受給条件が満たされている場合期限なし |
| 手続き場所 | 市区町村の生活困窮者自立相談支援機関 |
| 主な持ち物 | ・申請書 ・身分証 ・収入証明 ・預貯金残高がわかる書類 |
住宅確保給付金の詳しい手続きの流れや相談窓口については、厚生労働省のホームページで解説されています。
参考:厚生労働省生活支援特設ホームページ「住宅確保給付金」
引っ越しとあわせて本籍地も変更する場合の手続き
婚姻と同時に引っ越しをする場合など、本籍地の変更が必要になるときは転籍届を提出します。ただ、引っ越しにあわせて転籍するかどうかは本人の自由ですので、転籍届の提出期限はありません。転籍届は、旧本籍地、もしくは新本籍地を管轄する市区町村の役所に提出します。印鑑と本人確認書類が必要です。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

主要都市の市役所・区役所の連絡先
役所の手続きは、自治体ごとに異なる場合があります。必要書類や申請期間などもそれぞれ定められていることがあるため、二度手間にならないよう、あらかじめ自治体に確認しておきましょう。主要都市の市役所・区役所の連絡先は以下のとおりです。
北海道札幌市役所
代表番号:011-211-2111
コールセンター:011-222-4894
https://www.city.sapporo.jp/
宮城県仙台市役所
代表番号:022-261-1111
コールセンター:022-398-4894
https://www.city.sendai.jp/
愛知県名古屋市役所
代表番号:052-961-1111
コールセンター:052-953-7584
https://www.city.nagoya.jp/
東京都新宿区役所
代表番号:03-3209-1111
コールセンター:03-3209-9999
http://www.city.shinjuku.lg.jp/
東京都中野区役所
代表番号:03-3389-1111
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
東京都杉並区役所
代表番号:03-3312-2111
https://www.city.suginami.tokyo.jp/
大阪府大阪市役所
代表番号:06-6208-8181
コールセンター:06-4301-7285
https://www.city.osaka.lg.jp/
兵庫県神戸市役所
代表番号:078-331-8181
コールセンター:078-333-3330
https://www.city.kobe.lg.jp/
広島県広島市役所
代表番号:082-245-2111
コールセンター:082-504-0822
https://www.city.hiroshima.lg.jp/
福岡市北九州市役所
代表番号:093-582-2525
コールセンター:093-582-4894
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/
役所以外で必要な引っ越し手続きは?
引っ越しの際は、役所以外にも、電気・ガス・水道などライフラインの手続きや、警察署・会社などの手続きも必要です。たとえば、以下の手続きが必要です。
- 電気・ガス・水道、インターネット、電話などのライフライン手続き
- 賃貸物件や駐車場の解約・新規契約手続き
- 不用品回収
- 勤務先、通学先での住所変更手続き
- 各種保険や銀行などの住所変更手続き
- 運転免許証の住所変更、車庫証明、自動車の登録変更など
下記でも詳しくまとめています。
「引っ越し手続きのやることチェックリスト!タイミングや必要書類などまとめて解説」
「【引っ越しやることチェックリスト】手続きの順番・荷造りなど総まとめ」
役所手続きと併せてチェックリストで確認できるので、ぜひご活用ください。
引っ越しの手続きは煩雑です。どの手続きをどのタイミングで行えばよいか、期日や順番が分からなくなることもあるでしょう。手続き管理に不安な方に、引越れんらく帳がおすすめです。
引越れんらく帳は、転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約といった役所の手続き、電気・ガス・水道などライフラインの手続きをまとめて行えます。引っ越し日を設定すると各手続きの期日をアラートする機能もあり、手続きの抜け漏れ防止にも効果的です。登録は無料ですので、ぜひお気軽にご登録ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

転出届やライフラインの手続きは引越れんらく帳から一括で完了!
引っ越しの際は、転出届や転入届、転居届の提出、マイナンバーカードの住所変更手続きなど、役所での手続きが多く発生します。各手続きには期限があるので、自分に必要な手続きを漏れなくチェックしましょう。
本記事で紹介した役所手続き以外にも、引っ越しの際に必要となる手続きはたくさんあります。やるべきことをリストアップし、効率よく手続きを済ませるのがおすすめです。これから引越しを控えている人は次 の「引っ越しやることリスト」を利用しながら、スケジュールの管理に役立ててください。チェックリストをエクセルとPDFでダウンロードできます。
また、電気・ガス・水道などのライフラインに関する手続きも併せて簡単に済ませたい人には、引越れんらく帳の利用がおすすめです。引越れんらく帳は、インターネットで引っ越しに関する手続きをまとめて一括で完了できる便利なサービスです。1回の情報入力で転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約、複数のライフラインの手続きを済ませられます。引っ越しの手続きに関する負担を軽減したい方は、ぜひご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

◆引っ越し手続きのやることチェックリスト!タイミングや必要書類などまとめて解説
◆郵便局の転居届の提出方法と必要なものは?引っ越し先への転送・延長方法を解説