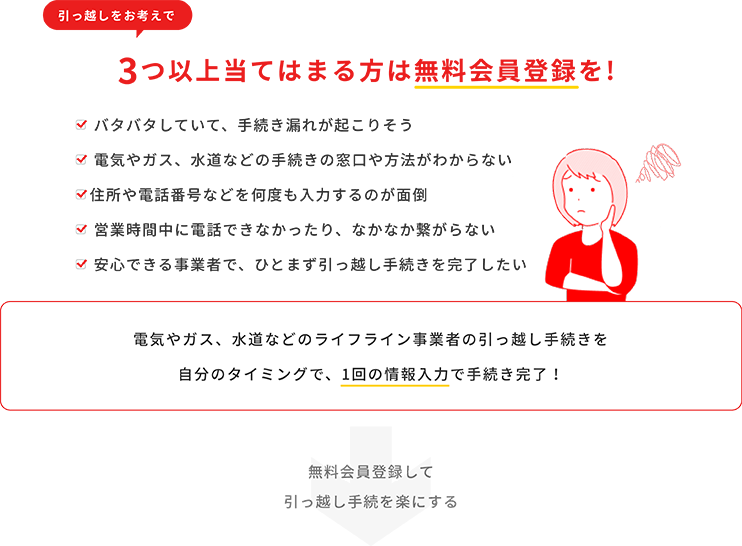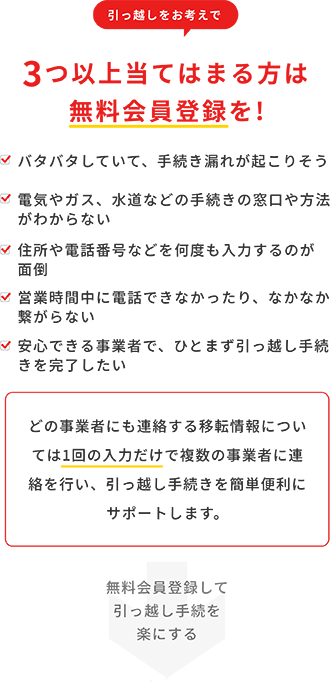引っ越しやることリスト完全ガイド|ライフラインや役所手続き・梱包作業を時系列で解説
引っ越しは、ライフラインの手続きや役所の手続き、梱包作業などやることがたくさんあります。引っ越しが決まったら、やることや必要なものをあらかじめ確認して、余裕を持って作業を開始しましょう。
この記事では、新しい生活をスムーズに始められるよう、引っ越しの前後でやることや手続きを45項目にまとめました。引っ越しの流れを事前に把握して、漏れの無いように手続きを済ませましょう。具体的な手順が分かるように「引っ越しやることリスト」も用意しているので、ぜひご活用ください。
【この記事でわかること】
引っ越しのやることは「物件決定後すぐ」「1か月~1週間前」「前日」「当日」「引っ越し後」の5段階です。役所手続き、電気・ガス・水道などのライフラインの停止や開始・住所変更は、早めのオンライン手続きで漏れを防げます。 また、「引越れんらく帳」のような一括申請サービスを使えば、ネットでまとめて申請可能です。
この記事の目次
◆引っ越しの大まかな流れと当日の動き方とは?必要なものや注意点
◆【電気・ガス・水道の引っ越し手続き】ライフライン手続きの手順や注意点を解説
◆引っ越し手続きのやることチェックリスト!タイミングや必要書類などまとめて解説
引っ越しでやること一覧!全体の流れを総ざらいしよう
主に引っ越し前後にやることは次のとおりです。引っ越しの準備を始める前に、あらかじめ把握しておきましょう。詳細は各見出しをご覧ください。
【フェーズ別主要タスク】
また、「できるだけ引っ越し手続きを簡略化したい!」という方には、無料サービス「引越れんらく帳」のご利用がおすすめです。一度住所などの情報を入力すれば、電気・ガス・水道などライフラインの手続きを一括で済ませることができます。手続きにかかる時間の削減につながるので、ぜひ利用してみてください。
上記の作業が主に引っ越し前後にやることです。引っ越しの準備を始める前に、あらかじめ把握しておきましょう。
また、「できるだけ引っ越し手続きを簡略化したい!」という方には、無料サービス「引越れんらく帳」のご利用がおすすめです。一度住所などの情報を入力すれば、電気・ガス・水道などライフラインの手続きを一括で済ませることができます。手続きにかかる時間の削減につながるので、ぜひ利用してみてください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越し先の物件が決まったら最初に何をすべき?すぐにやることリスト
引っ越し先の物件が決まったら、退去日と移動手段を最優先で確定し、余裕をもって引っ越し準備を進めるために、できることから早めに着手します。まず、引っ越し先の物件が決まってからやるべきことは主に6つです。
|
|
項目 |
チェック |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
また、物件が決まった段階で無料のWebサービス「引越れんらく帳」に登録しておくのがおすすめです。「引越れんらく帳」を使うと、手続きができる電気ガス水道の事業所が一覧で出てくるため、個別に調べる手間が省けます。
また、電気・ガス・水道以外のインターネット・NHKなどの手続きも合わせて完了できます。24時間いつでもスマホから手続きできるので、引っ越し準備が一気に楽になります。登録は30秒で完了しますので、早めに登録しておきましょう。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

1.旧居の退去日を決定
引っ越しする新居が決まったら、次に旧居の退去日を決めます。
物件によって異なりますが、旧居の解約予告は、退去の1~2か月前までに行う必要があるため、忘れずに行いましょう。また、退去月の家賃が日割り計算になる場合もあれば、退去日が月末に設定されているケースもありますので、入居の際の契約書を確認しましょう。
退去日は、引っ越し当日に設定し、旧居の鍵を返却してから新居に移動できるとスムーズです。
2. 引っ越し業者またはレンタカー、ホテルの手配・引っ越し日を決定
旧居の退去日が決まったら、引っ越しの日程と方法を検討します。複数の引っ越し業者から見積もりをもらって比較すると、違いがわかりやすくなります。
引っ越し業者に依頼する場合、退去の通知をする都合上、引っ越し予定日の2か月~1か月半前には見積もりを取り、引っ越し業者を予約するのが理想的です。特に、繁忙期である2月~3月頃は予約がとりにくいため、なるべく早めに動きましょう。繁忙期以外でも、土日祝や大安、午前中などは予約が埋まりやすい傾向です。 また、早めに業者を決めることで、引っ越し費用を抑えられるメリットもあります。
なお、引っ越し費用を抑えるなら、引っ越しする人が少ない8月頃や、11月頃がおすすめです。引っ越す日の曜日や六曜、時間帯により引っ越しの料金は多少上下するものの、ほかの時期より安く引っ越しができるでしょう。
引っ越しを考えている方の中には、業者に頼らず自力で行おうとする方もいるでしょう。自分で引っ越しを行う場合、費用を抑えられるメリットがありますが、家具や家電を傷つけたり、破損させてしまうリスクが高まります。
また、荷造りから運び出し、運搬、搬入までの作業をすべて自分や家族で行う必要があるため、手間と時間がかかる点も注意が必要です。荷物の量や体力、時間的な余裕、家財道具の価値など、さまざまな要素を考慮して慎重に検討しましょう。
業者を利用せず、自力で引っ越す場合は、必要に応じてレンタカーを手配してください。その場合は、1か月前など早めにトラックのレンタルを済ませましょう。また、引っ越し当日に利用する駐車場も併せて事前に確認しておくとスムーズです。
引っ越しの方法と日程が決まったら、新居の不動産会社に連絡を入れてください。
遠方への引っ越しでは、新幹線や飛行機、レンタカーなどの手配も忘れずに行いましょう。早めに予約することで、割引が適用されることもあります。ペットと一緒に移動する際は、各交通機関の規定を事前に確認しておくと安心です。さらに、明け渡しのタイミングが合わず新居にすぐ入居できないケースもあるため、その際は、お近くのホテルを利用するのもおすすめです。事前の予約も忘れずに準備しておきましょう。
◆2024年-2025年版|引っ越しに縁起の良い日取り・ダメな日取りカレンダー
◆引っ越しの訪問見積もりはメリット大!依頼から当日までの流れ、注意点を解説
◆引っ越し繁忙期はいつ?料金相場や閑散期との違い、安くするコツを解説
◆引っ越しの安い時期はいつ?曜日や時間帯、家賃が安い時期もまとめて解説!
3.賃貸物件の解約手続き
賃貸物件にお住まいの方は、賃貸契約書の内容を確認したうえで、管理会社や大家さんに退去の連絡を入れましょう。連絡方法は、郵送やFAXなど書面形式が一般的です。退去日の1か月~2か月前までに連絡が必要なケースが多いですが、契約内容により異なる場合もあります。解約手続きが遅れると、翌月の家賃の支払いが増えるおそれがあるため、忘れずに連絡しましょう。
◆賃貸をスムーズに解約!退去手続きの流れや違約金を避けた引っ越しのコツを紹介
4.駐車場の解約・新規契約はどう進める?
駐車場は「解約期限」と「契約手続き」に注意が必要です。旧居では、個人契約なら1か月前、法人契約なら1〜3か月前の告知が一般的です。契約書の規定を必ず確認しましょう。新居では、管理会社やオーナーへ連絡し、申込書・本人確認書類・車検証などを提出して契約します。引っ越し後15日以内に車庫証明の住所変更も忘れずに行いましょう。
旧居の駐車場の解約
駐車場の解約は期日遵守です。個人経営と法人経営の場合で、次のような違いがあります。
| 区分 | 通常の告知期限 | 手続きの特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 個人経営の場合 | 引っ越しの1か月前までに解約を告知するのが一般的 | 契約書に明記されていない場合でも、1か月前の連絡を基準にするとスムーズです。 |
| 法人経営の場合 | 契約内容により1~3か月前の告知が必要 | 賃貸借契約書に「解約予告の告知期限」が規定されているため、必ず契約書を確認してください。規定によっては2~3か月前の申し出が求められることもあります。 |
新居の駐車場の契約
駐車場の解約が終わったら、新居の駐車場の契約をしましょう。まずは契約したい駐車場を見つけ、管理会社や不動産会社、オーナーに連絡します。希望の駐車場の契約内容を確認したら、所定の申込書類に記入・捺印し、必要書類とともに提出します。必要書類には、運転免許証のコピー、車検証のコピー、証明書などがあります。新規駐車場の契約に必要な車庫証明書の住所変更は、引っ越し後15日以内に管轄の警察署で行います。運転免許証の住所変更手続きと同時に届け出ると、労力が少なく済むのでおすすめです。新居の駐車場の契約の手順は次のとおりです。
|
手順 |
①立地や料金などを考慮して駐車場を見つける ②管理会社あるいは不動産会社、オーナーに連絡 ③契約内容の確認 ④申込書類、必要書類を提出 ⑤車庫証明書の住所変更(警察署) |
|
必要書類 |
所定の申込書類、運転免許証のコピー、車検証のコピー、証明書など |
|
備考 |
・車庫証明書の住所変更は、引っ越し後15日以内に管轄の警察署で行う ・運転免許の住所変更手続きを併せて行うと効率的 |
5.ネット・固定電話・テレビの住所変更はいつまで?
ネットは最長2か月前から、工事が必要なケースに備えて前倒しが安全です。固定電話は移転手続き・番号変更の可能性に注意しましょう。
さらに詳しく見ていきましょう。
インターネット
インターネットについては、引っ越し先で現在の回線事業者やプロバイダが利用できないケースもあります。そのため、旧回線や旧プロバイダに新住所を連絡し、利用可能か確認する必要があります。使用中のインターネット回線・プロバイダとの契約を継続する場合には、インターネットの移転を行います。どこでも使えるモバイルWi-Fiなどを契約しているケースでも、住所変更手続きが必要です。インターネットの移転は時間がかかる可能性があるため、1か月前には手続きを済ませましょう。戸建て住宅に引っ越す場合などは、設備が整備されておらず、工事が必要になる可能性があります。そのため、2か月~1か月前に手続きを済ませておくのが無難です。
◆プロバイダを乗り換える方法とは?基本的な手順や比較ポイント
◆賃貸物件でインターネットを使うには?ネット「完備」と「対応」の違いも解説
◆初めてのインターネット回線契約!初心者でもわかる超入門ガイド
固定電話
固定電話は、業者へ電話、もしくはインターネットから移転手続きを行います。NTT東日本の管轄エリアからNTT西日本の管轄エリアへ引っ越す方は、それぞれで手続きが必要ですので、ご注意ください。電話工事は予約制となるため、混雑しやすい繁忙期は、早めに申し込むと安心です。固定電話を利用している場合、引っ越し先によって電話番号が変わることがあります。IP電話や光電話を契約している場合は、引っ越し後も基本的に同じ番号が使えますが、プロバイダの解約や別の会社との契約により、電話番号が変更される可能性があるため事前に確認をしておくと安心です。また、固定電話の住所変更と併せて、携帯電話やスマートフォンの住所変更も忘れずに済ませましょう。
衛星テレビ・ケーブルテレビ
衛星放送やケーブルテレビに関しても、新居が提供エリア内かどうかを事前に確認し、場合によっては解約や他のサービスへの乗り換えも検討しましょう。
衛星テレビは、ホームページ上から簡単に手続きが可能です。契約している衛星放送の会員ページにログインし、新住所を入力しましょう。ケーブルテレビを解約する際には設備の撤去工事が必要となることもあるため、早めの手続きを心がけることが大切です。
6.旧居で契約している火災保険や地震保険の解約手続き
旧居の住所で契約している火災保険や地震保険の解約も忘れずに行いましょう。
7.転居はがきや挨拶メールの作成
引っ越しの際は、お世話になった方や、関係各所へ挨拶状を送りましょう。送付のタイミングは、引っ越し完了後1か月以内に送るのがベストです。引っ越し直前や新生活が始まってからだと、慌ただしかったり、忘れてしまったりするため、引っ越しをすると決めたタイミングで作成しておくと安心です。特に、上司や先輩、友人や知人といったように、相手にあわせて挨拶状を作成するようにします。準備が難しい場合は年賀状の中で引っ越しの報告をするというのも一つの方法です。
また、近年では転居はがきを送らない方も増えてきました。紙はがきの代わりに、メールやLINEなどのSNSを活用している方も珍しくありません。特に、SNSはデザインフォーマットも充実しているため、簡単にオシャレな挨拶文を作成できます。相手との関係性にもよりますが、普段はがきのやり取りをしない仕事相手や友人相手であれば、メールやSNSでの報告で問題ないでしょう。
引っ越しの1か月~1週間前までにやることは?
引っ越しの1か月前から1週間前までというのは、引っ越しを目前に控えて忙しくなる時期です。不用品の処分、転出届の提出、ライフラインの手続き、荷造りの開始など、やるべきことが集中します。手続きを引越し前に慌てないよう一つひとつ着実に済ませましょう。
|
|
項目 |
チェック |
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
8.不用品・粗大ごみの処分
引っ越し前に不用品を処分しておくと、新居での片付けの手間が省けます。不用品は、リサイクルショップ・インターネットオークション・フリーマーケットアプリなどを利用して販売するのも一つの手です。また、引っ越し業者の中には、不用品の買取や有料での不用品処分サービスを行っている会社もあります。 一方で、粗大ゴミ扱いになるものを捨てるときは、自治体や専門業者に依頼が必要です。特に繁忙期などは、粗大ごみの回収予約が埋まっている場合が多いため、早めに予約をとりましょう。
◆引っ越しで不用品処分する方法は?引っ越し業者や回収業者の特徴を解説!
9.家電製品・パソコンの処分
家電製品は、種類によって処分方法が異なります。中でも、エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビは、家電リサイクル対象となっており、自治体の粗大ごみでは処分できません。これらの家電製品を処分する際は、下記のいずれかの方法を選択します。
- 家電リサイクル受付センターに回収を依頼する
- 指定取引場所に直接持っていく
- 購入した家電量販店で処分してもらう
処分の際は、家電リサイクル料金+収集運搬料金を支払う必要があるため、あらかじめ確認しましょう。
その他の、小型家電(ドライヤー、プリンター、掃除機、電子レンジなど)に関しては、「小型家電リサイクル法」にもとづいて処分します。自治体ごとに、市役所やスーパー、家電量販店などに無料回収ボックスが設置されているので、そこに入れれば処分費用は掛かりません。
また、パソコン等の小型家電を、宅配便でご自宅から回収・リサイクルする「宅配便リサイクル」を活用するのもおすすめです。Webサービス「引越れんらく帳」を使うと、電気・ガス・水道などの住所変更手続きと合わせて、リネットジャパンが提供している宅配便リサイクルを申し込むことができます。できるだけ時短したい方は、ぜひ活用してみてください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

10.新居の間取り図の作成、必要なものの準備
新居の内見をするとき、事前に部屋の寸法を測っておくと、引っ越しに向けた買い物がしやすくなります。新居の玄関やドアの幅や、戸建住宅の場合は階段の高さなども計測しておくと、家具や家電を搬入できるかどうか判断するのに役立ちます。測った寸法をもとに間取り図を作成し、家具や家電は何を購入するか、配置はどうするのかを考えておきましょう。サイズの大きな家具や家電は、新居に直接配送してもらうと負担が少なくなります。間取り図をもとに、新居に合った生活必需品を準備しましょう。
◆引っ越しで大型家電・家電を運んでもらう場合の注意点と、買い替えのタイミング
◆無料で家具配置をシミュレーション!おすすめアプリ10選【3D/AR/2D】
◆はじめてのお部屋探しで内見時にチェックすべき16のポイントと持ち物
11.荷造り(使用頻度の低いもの)
引っ越し業者を利用する場合は、事前に梱包するものと当日までしなくてよいものをご確認ください。基本的には、使用頻度の低いものや重いものから先にダンボール箱へ詰めていきます。オフシーズンの洋服や来客用の食器、非常用の食品、日用品のストック、書籍、CDなどは使用頻度が低いので、早めに着手するとよいでしょう。
荷物を詰めたダンボール箱には、油性ペンで中身を明記します。さらに、新居の間取り図に番号を振っておき、ダンボール箱に運搬する部屋の番号を書いておくと、効率よく運び込みを進められるうえ、作業負担も軽減できます。荷造りは、遅くとも引っ越しの2~3日前までに終わらせておくのが理想です。
◆【引っ越しのコツ】荷造りから荷解きまで効率よく進めるには?
12.梱包資材の準備
荷造りに備えて、ダンボール・ガムテープ・養生テープ・緩衝材・新聞紙・ビニール袋などの梱包資材を揃えておきましょう。引っ越し業者から無料で提供してもらえる場合もありますが、梱包資材の追加料金が発生するケースもありますが、自分で調達しておく必要があるケースもあります。その際は荷物量に合わせて梱包資材をご用意ください。
◆荷造りに役立つ紐の結び方と、トラックの荷台に荷物を固定する方法
◆引っ越し用ダンボールの調達方法!選び方や組み立て・梱包のコツも
◆ハンガーボックスとは?引っ越し時に衣類を畳まずに運搬したい!荷造り時の活用方法
13.転出届の提出(異なる市区町村への引っ越しのみ)
引っ越しで住所が変わる場合、役所で「転出届・転入届」または「転居届」の手続きが必要です。このうち、引っ越し前に提出が必要なのは「転出届」です。
異なる市区町村に引っ越し→転出届・転入届を提出
転出届は、現住所と異なる市区町村へ引っ越す場合に提出します。転出届は、旧住所を管轄している役所・役場に、引っ越しの14日前〜当日までに提出しなければなりません。引っ越し後は、新しい住所を管轄する役所・役場で転入届を提出します。(転入届については、後述する34の項目で詳しく解説します。)
この際、「転出証明書」が発行されますので、大切に保管しておきましょう。この転出証明書は、転入届を提出する際に必要です。人によっては、併せて印鑑登録の廃止や国民健康保険の資格喪失届、児童手当の受給事由消滅届などの手続きも必要となります。転出手続きの際には、それらの手続きをまとめて行うと効率的です。
同一市区町村に引っ越し→転居届を提出
転居届は、現住所と同じ市区町村に引っ越す場合に提出します。転居届は、引っ越し後14日以内に役所・役場に提出しなければなりません。こちらも同様に、人によって国民健康保険や児童手当の住所変更が必要となるため、あらかじめご確認ください。(後述する34の項目でも解説します。)
また、転出届の提出は役所・役場に行かずとも、「引越れんらく帳」やマイナポータルでオンライン手続きできます。詳しくは「引越しワンストップサービスのやり方を解説!転出届をマイナポータル・引越れんらく帳からオンライン提出!」の記事をご覧ください。
◆引っ越し時に役所でやること・手続きの順番一覧!住所変更方法と必要書類まとめ
◆転出届の提出はいつからいつまで?引っ越し後でも大丈夫?
◆転出届・転入届・転居届に必要な書類は?提出方法と合わせて解説
◆引っ越し時に住所変更しないとどうなる?住民票の異動はいつまで?リスクと手続き方法を解説
引っ越しでは、転出届・転入届の提出に加え、ライフラインやNHKの住所変更など、さまざまな手続きが必要です。
「引越れんらく帳」なら、転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約だけでなく、電気・ガス・水道などのライフラインの使用停止・開始、NHKの住所変更などをオンラインで手続きできます。複数の手続きを一括で申請できるほか、手続き漏れ防止のアラート機能も提供しています。引っ越しの際は、ぜひ「引越れんらく帳」をご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

14.子どもの転校・転園手続き
家族に学校へ通う子どもがいる場合には、転校や転園の手続きも必要になります。引っ越しの日程が決まった段階で、早めに転校・転園する旨を連絡しましょう。
現住所と異なる市区町村への引っ越しで保育園を転園する場合には、通っている保育園を退園するために退園届の提出が必要となります。転園の手続き後は、転入先の地域の保育園について調べて、入園の申し込みを行います。
幼稚園を転園する場合には、まず希望する幼稚園に空きがあるのか、途中入園が可能かどうかを確認します。次に現在通っている幼稚園に転園を伝え、在園証明書などの転入に必要な書類をもらいます。入園願書、住民票、今通っている幼稚園の在園証明書を用意し、入園の手続きをします。引っ越し先の市区町村や園によっては、必要書類の内容が違う場合もあるので、必ず必要書類の内容を事前に確認してから、手続きを進めるようにしましょう。
転校をする場合には、転校がわかったら早めに担任の先生に申し出ます。最終登校日には、転校の必要書類である「在学証明書」を学校から受け取ります。その後は転校先の市区町村の役場へ書類を提出し、転校の手続きを行う流れになります。
|
|
手順 |
|
保育園 |
①退園届の提出 ②転入先の保育園に入園申し込み |
|
幼稚園 |
①転園先の空状況、途中入園可能か、必要書類を確認 ②在園中の幼稚園に転園を伝える ③在園証明書などを受け取る ④転園先に在園証明書、住民票、入園願書など必要書類を提出 |
|
小学校・中学校・高校など |
①在学中の学校に転校の申し出をする ②在学証明書を受け取る ③転校先の市区町村役場に書類を提出 |
◆高校の転校手続きの流れ│転入先を決める際の注意点と準備するもの
◆中学校の転校手続きの流れとは?転入先を決める際の注意点や準備するものを解説
◆小学校を転校する際の手続きと住所変更に伴い準備すべきことを解説!
◆幼稚園を転園する方法とは?引っ越しで必要な手続きや注意点を解説
◆引っ越しで保育園を転園する際の手続き方法と転園時の確認事項
15.勤務先への住所変更の届出
引っ越しで住所変更をする場合には、会社にも忘れずに届け出をしましょう。住所変更の届け出は税金、社会保険料の手続きや通勤手当の支給に関わる大切なことです。引っ越し予定日・住所が分かったら早めに総務部・人事部などの担当部署に報告します。所定の書類などがある場合はそれに従い、住所と通勤方法(経路)の変更を届け出ましょう。
◆引っ越したら会社に報告する?届け出が必要な理由は?住所変更の報告タイミングと伝え方を解説
16.ライフラインの手続き
電気・ガス・水道を含むライフラインの停止・開始手続きを行いましょう。手続きを行わないと、引っ越し後も旧居のライフライン料金が請求される可能性があります。電気はインターネットまたは電話で手続きが可能です。ガスは業者により異なりますが、基本的には電話で連絡を行い、場合によってはインターネットで手続きできる可能性もあります。回線に立ち会いが必要となるため、必ずガス会社へご連絡ください。水道はインターネットまたは電話から管轄の水道局へ連絡して手続きを行います。
なお、「引越れんらく帳」を使えば、電気・ガス・水道や固定電話、NHKなどの引っ越し手続きをまとめてWebから完了できます。会社によって異なる手続きの方法を一本化することができますので、ぜひご活用ください。
◆【電気・ガス・水道の引っ越し手続き】ライフライン手続きの手順や注意点を解説
◆【ガスの開栓・停止】引っ越し時のガス手続きの流れを解説!立ち合いは必要?
◆引っ越し時のNHKの住所変更手続き方法を解説!解約の対象は?受信料は?
忙しい引っ越し手続きを効率よく行うには、「「引越れんらく帳」が便利です。電気、ガス、水道等の手続きをインターネット上で一括申請できますので、ぜひご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

17.住所変更が必要なその他サービスの手続き
その他に利用しているサービスでも住所変更が必要です。例えば、新聞や定期購読誌の配達先、クレジットカード会社・保険会社・銀行・証券会社、NHK、ウォーターサーバー、牛乳配達、通信販売(ECサイト、ネットスーパー、フードデリバリーサイト等)の支払いなどはその一例といえます。さらに、インターネットで登録しているショッピングサイトやサブスクリプションサービスも忘れずに住所を更新しましょう。現住所で契約しているサービスをご確認ください。解約する場合は、月の解約期限を過ぎないよう注意が必要です。
配送サービスの多くは、インターネット上で住所変更が可能ですが、なかには電話や郵送で行う必要がある場合もあるため、しっかりと確認しましょう。
◆クレジットカードの住所変更方法。引っ越し後、変えなかった時のデメリットも解説
◆引っ越ししたら銀行の登録住所は変更すべき?手続きの流れと注意点
◆保険の住所変更はいつまでに?大手14社のオンラインでの手続き方法は?
18.郵便物の転送手配
旧居に届く郵便物を、新居に無料で転送する手続きを行うと、引っ越し後も郵便物の受け取りでトラブルが起こりにくいため便利です。転送期間は手続きから1年間です。転居届の用紙に必要項目を記入し、最寄りの郵便局へ提出もしくはポストへ投函しましょう。忙しい方はインターネットで手続きできる「e転居」もご活用ください。
◆郵便局の転居届の提出方法と必要なものは?引っ越し先への転送・延長方法を解説
郵便局の転送だけでなく、引っ越しでは水道・電気・ガス・インターネットなど、さまざまな住所変更が必要です。「引越れんらく帳」を使えばライフラインの手続きを一度に済ませられます。ぜひ「引越れんらく帳」をご利用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越しの前日までに何を準備すれば安心?
引っ越し直前の荷造り、家電の引っ越し準備などを済ませます。チェックリストを確認しながら、引っ越しの当日前にやるべきことを予習しておきましょう。
|
|
項目 |
チェック |
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
19.荷造り(使用頻度の高いもの)
引っ越しの5日前~前日ごろになったら、家具の解体や家電梱包、引っ越し当日まで使用するものの梱包を行います。以下のものは前日まで使用する可能性があります。
- キッチン用品
- ランドリーグッズ
- 洗面用品
- 女性の化粧道具など
引っ越し当日まで使う可能性がある物は、当日までダンボールの封をせずに置いておくと必要なタイミングで取り出しやすくなります。使い終わったものからどんどん段ボールに詰めていくようにすると、荷造りがスムーズです。また、引っ越し先ですぐに使用するものは、ひとつの箱にまとめて入れておくのもよいでしょう。その際は、引っ越し業者が引越し先に到着してすぐ搬入できるように、最後にトラックに入れてもらうように伝えてください。
◆引っ越しの荷造り完全ガイド!効率よくすすめるコツ、用意する物から手順まで解説
◆引っ越し時の靴の荷造りはどうする?梱包のコツと注意点を解説!
20.食品の整理
引っ越しの前日までに、冷蔵庫の中身を処分しておきましょう。すぐに食べ切れないものや、処分できないものがある場合には、クーラーボックスに入れて一時的に保管する方法もあります。
◆引っ越しの前日は何をするべき?確認事項や準備するもの、過ごし方
◆キッチン断捨離の方法|引っ越し時に行いたい、ものの捨て方、残し方
21.挨拶用の手土産を用意
新居で挨拶回りをするときの手土産を用意しましょう。一戸建ての場合には両隣の3軒、アパートやマンションの場合は上下階と両隣に挨拶するのが一般的です。なお、単身者の場合は挨拶をしないこともあります。近年は防犯上の理由から挨拶をしない女性も多いため、状況に応じてご判断ください。
◆引っ越し挨拶の粗品に熨斗(のし)は必要?付ける理由とマナーを解説
◆引っ越し挨拶は必要?喜ばれる粗品の選び方や金額の目安を紹介!
22. 新居の掃除や下見
入居前に、新居の掃除や下見をしておくことも大切です。新居を細かく掃除することで、細かいほこりや汚れを取り除くことはもちろん、部屋の傷や不具合を事前に確認できます。見つけた傷や汚れなどは、日付がわかるように写真撮影しておくとよいでしょう。あとで新居を退去する際に修繕費を請求されても、入居前からの傷や不具合であることを証明できます。また、荷物の搬入前に掃除や下見をしておけば、万が一搬入時に破損があった場合、破損がいつできたものか判別しやすくなります。もし設備や部屋に大きな問題があるようであれば、管理会社や大家さんに気づいた時点で連絡するようにしましょう。
◆【新居の掃除方法】引っ越し前に掃除が必要な理由とは?
◆入居前にやることリスト17項目!引っ越し前の新居の掃除・準備方法
23.パソコンのバックアップ
パソコンは丁寧に梱包するだけではなく、事前にデータのバックアップも取っておきましょう。万が一引っ越し中に破損してしまった場合、パソコンは新しいものに買い替えることはできても、データの復旧まではできない場合があるため、あらかじめ別の場所にバックアップデータを残しておきましょう。バックアップは外付けHDD、USBメモリ、メディアディスク、クラウドサービスなどを使って行います。それぞれバックアップできるデータ量に違いがありますので、データ容量に合わせて最適な方法を選ぶといいでしょう。
24. テレビなどの映像機器・オーディオ機器の配線まとめ
家具・家電の搬入や配置は引っ越し業者に行ってもらえますが、配線は基本的に自分で直すことになります。何もしないままだと引っ越しの際に配線をどんどん抜かれてしまい、あとになってどの機器の配線かわからなくなってしまいます。事前に自分で配線をまとめておくようにしましょう。どの機器に接続されているかを確認しながら、一本ずつ配線を抜いていきます。抜いた配線は養生テープでまとめて、名称を書いておくとわかりやすいです。このとき、同じ家電の配線はまとめてしまっておくと後になって復旧が楽になります。
◆引っ越し時、家具は新居に持っていく or 買い替え?処分する時の費用と配送時の注意点を解説!
25.引っ越し当日の段取り確認
引っ越し当日は慌ただしくなることが予想されます。前日までに段取りを確認し、当日にスムーズに作業ができるようご準備ください。引っ越し業者への指示出しや、近隣の方への挨拶、最終的な荷造りなど、当日の流れをイメージしながら、必要なことをメモしたりリストアップしたりしておきましょう。なお、引っ越し当日に、荷物を搬出した後、予想以上に旧居が汚れている可能性もあります。掃除道具を準備しておくのがおすすめです。
また、光熱費や引っ越し料金の現金精算など、まとまった金額の現金が必要になることがありますので、あらかじめ確認して準備しておきましょう。
引っ越し当日は人の出入りが多いので、貴重品は常に身につけ、財布や実印、預金通帳などの貴重品は段ボールに詰めるのではなく、手荷物で運びましょう。
引っ越しのライフライン手続きをオンライン上でまとめて行いたいなら、「引越れんらく帳」が便利です。無料でサービスを利用できますので、ぜひご活用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

26.冷蔵庫と洗濯機の水抜きとコンセント抜き
引っ越し前日に、冷蔵庫および洗濯機の「水抜き」と呼ばれる作業を行います。
冷蔵庫
冷蔵庫は、コンセントを抜き、翌日水受けに溜まった水を捨てましょう。コンセントを抜いて一晩おいておくと、冷蔵庫と冷凍庫内が濡れた状態になりますので、十分に水気をふき取って乾かします。
洗濯機
洗濯機は、蛇口を閉めた状態で、給水ホースと排水ホースの水を抜き、取り外しておきます。水抜きの詳しい方法は、取扱説明書でご確認ください。
◆冷蔵庫の運搬方法は?横倒しOK?注意点や引っ越し業者の費用も解説
◆【引っ越しで洗濯機を運ぶ方法】1人でも大丈夫?横にしてもOK?業者に頼む?事前準備は?
27. 旧居の掃除やごみの最終処分
旧居の掃除
引っ越し後、数日たつと、旧居にはハウスクリーニングが入ります。しかし、賃貸物件の退去時には、入居者は原状回復をする義務があります。そのため、自分でも旧居の掃除が必要です。壁や床、水回りなど、汚れが目立つ部分は念入りに掃除をしておきましょう。
ごみ捨ての計画
引っ越しのために片付けや荷造りをしていると、ごみがたくさん出ます。自治体の定めるごみ回収日に捨てられるよう、計画的に準備を進めましょう。もしも引っ越し当日にごみが出たり、捨てきれずに残ったりした場合は、新居で捨てるか直接ごみ処理場に持ち込んで捨てるようにします。なお、ごみ処理場に直接持ち込む場合は、ごみの持ち込み方や費用などを事前にホームページでご確認ください。
28.レンタルものや個人的に借りているものの返却
引っ越すと、返却することが簡単ではなくなる場合があります。たとえば、図書館やレンタルショップで借りたものや、友人などから個人的に借りたものなどを忘れないように返却しましょう。
◆引っ越し時の旧居のお掃除どこまでする?退去時の掃除のコツを場所別に解説
引っ越しの当日はなにをする?
引っ越し当日は、主に最終梱包→搬出→精算→明け渡し→新居開栓・挨拶の順で進めます。旧居と新居の両方で作業を行うため、効率よく動けるよう工夫が必要です。前日に確認した段取りの通りに進行しましょう。
|
|
項目 |
チェック |
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
|
34 |
|
|
|
35 |
|
◆引っ越し当日のやるべき準備と注意点は?事例から学ぶトラブル対策
29.荷物の最終梱包と搬出
引っ越し当日に使用していたものをダンボール箱にまとめて最終的な荷造りを行い、新居ですぐに使えるようにします。代表者が引っ越し業者へ指示を出しましょう。荷物が搬出されたら掃除を行います。
30.電気・ガス・水道の閉栓と精算
電気・ガス・水道などライフラインの手続きは事前に済ませてあるため、基本的に当日に行う作業はありません。ただし、ガスの閉栓に立ち会いと精算が必要な場合があります。あらかじめご確認ください。
◆引っ越し時のガスコンロの正しい取り外し方は?テーブルコンロの安全な設置の流れと方法、注意点
◆水道の停止・開始手続きに立ち会いは必要?引っ越し当日から使える?
◆【ガスの引っ越し】停止・開始手続きを解説!立ち会いに間に合わない場合は?
31.旧居の掃除
旧居から荷物を搬出したら、掃除を行います。きれいな状態で退去できれば原状回復にコストがかからず、敷金が返金される可能性があります。水回りや壁、床、窓など、汚れが目立つ場所を集中してきれいにしていくようにしましょう。
◆引っ越しの際の持ち物リスト|必携アイテムを完全チェック!
◆引っ越し時の旧居のお掃除どこまでする?退去時の掃除のコツを場所別に解説
◆賃貸の退去費用の相場は?原状回復義務や払えない場合の対処法を解説
32.旧居の明け渡し・鍵返却
旧居が賃貸物件の場合は、鍵の返却を行います。このとき、不動産会社の立ち合いのもと、旧居の傷や汚れをチェックします。鍵の返却方法は借りている物件によりますので、あらかじめ不動産会社に連絡して、返却方法や時間を確認しておきましょう。
33.引っ越し料金の精算
引っ越し料金の精算を行います。精算のタイミングは業者により異なりますが、作業開始前に支払いを済ませるのが一般的です。ほかに、銀行振り込みで精算するケースや、後払いのケースもあります。
34.電気・ガス・水道の開栓・開通
新居にて、電気・ガス・水道などライフラインの開栓を行います。電気のブレーカーを上げ、水道の元栓を開けましょう。ガスは業者の立ち会いのもとで、開栓してもらう形になります。
◆引っ越し当日に電気を開通する方法|事前手続きが必要なパターンは?
◆【ガスの開栓・停止】引っ越し時のガス手続きの流れを解説!立ち合いは必要?
35.管理人・ご近所への挨拶
新居に到着したら、近所の方へ挨拶回りをします。引っ越し作業で迷惑をかける可能性を考慮して、可能であれば作業の前に挨拶を済ませたほうが安心です。新居で快適な生活を送るためには、近隣の方からの理解が欠かせません。忘れずに挨拶を済ませておきましょう。
◆引っ越し挨拶の粗品に熨斗(のし)は必要?付ける理由とマナーを解説
◆引っ越し挨拶は必要?喜ばれる粗品の選び方や金額の目安を紹介!
引っ越し前後は、荷造りや挨拶などさまざまな作業が立て込みます。ライフラインの手続きは、「引越れんらく帳」を利用して一括で済ませておきましょう。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越し後に必ずやることは?
新居への引っ越しが完了したら、新住所で暮らすため、14日以内の役所対応を最優先で手続きを済ませしましょう。ここでは、役所関係・自動車・ペットなどの手続きについてお伝えします。
|
|
項目 |
チェック |
|
36 |
|
|
|
37 |
|
|
|
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
44 |
|
|
|
45 |
|
36.転入届・転居届の提出
引っ越しが完了したら、転入届または転居届を所轄の役所・役場に提出します。転入届は、他の市区町村に引っ越しをした場合に提出します。引っ越し当日から14日以内に、新住所を管轄している役所・役場に提出してください。
転居届は、これまでと同じ市区町村内で引っ越しをした場合に提出します。引っ越し当日から14日以内に、管轄する役所・役場で手続きを済ませましょう。
37.その他役所での手続き
引っ越し先の役所で転入届を提出する際に、役所で行う他の手続きも行うと効率的です。
- マイナンバーカードの住所変更手続き
- 印鑑登録
- 国民健康保険の加入
- 国民年金の住所変更
- 児童手当の認定申請
◆引っ越し時に役所でやること・手続きの順番一覧!住所変更方法と必要書類まとめ
◆引っ越し後はマイナンバーカードの変更手続きが必要!手順や期限を解説
◆引っ越し時、印鑑登録の住所変更手続きは必要?印鑑証明書の申請時に必要なものを解説
◆引っ越し時の保険証の住所変更手続き方法を解説!期限はいつまで?
◆引っ越した際、年金の住所変更に手続きは必要?手続き方法をわかりやすく解説!手順から注意点まで
◆引っ越しに伴う児童手当の住所変更手続き方法と必要なものをわかりやすく解説
38.転入先の学校や幼稚園、保育園での手続き
転入先の保育園、幼稚園、学校で子どもの転園・転校手続きを行います。ここでは転園・転校前の学校で受け取った書類が必要です。市区町村の役所の窓口で手続きを済ませたうえで、園や学校へ必要書類を提出してください。転入する学校や園によって手続きは異なるため、事前に窓口で確認してください。
|
|
必要書類の一例 |
|
幼稚園 |
入園願書、住民票、今通っている幼稚園の在園証明書(いつからいつまでその園に通っていたかを証明する書類) |
|
公立小中学校 |
在学証明書、教科書給与証明書、入学通知書 |
◆高校の転校手続きの流れ│転入先を決める際の注意点と準備するもの
◆中学校の転校手続きの流れとは?転入先を決める際の注意点や準備するものを解説
◆小学校を転校する際の手続きと住所変更に伴い準備すべきことを解説!
◆幼稚園を転園する方法とは?引っ越しで必要な手続きや注意点を解説
◆引っ越しで保育園を転園する際の手続き方法と転園時の確認事項
39.自動車やバイク関連の登録内容を変更
自動車やバイクをお持ちの方は、登録されている住所を変更する必要があります。自動車の場合は車検証の住所変更や車庫証明の手続き、バイクの場合は住所変更の登録手続きを行います。また、免許証の住所も併せて変更します。都道府県内の運転免許更新センター、運転免許試験場、地域の警察署のいずれかに必要書類をそろえて行き、窓口で手続きをしてください。
◆引っ越し時の車の手続きまとめ!車検証・車庫証明の住所変更方法を解説
◆引っ越し時、免許証の住所変更はいつまで?手続き時間や必要書類を解説
40.不動産登記の住所変更
土地や建物を所有している場合、引っ越しなどで住所が変わった際に「所有権登記名義人住所変更登記」という手続きを行う必要があります。この手続きでは、登記簿(不動産の登記記録)の所有者欄に記載されている住所を新しい住所に更新します。なお、この住所は自動的に変更されないため、所有者が自ら手続きを申請しなければなりません。手続きを行うには、申請書、転出先の住民票(住所証明書)、および印鑑(認印)が必要です。
2021年(令和3年)に不動産登記法が改正され、2026年(令和8年)4月1日から住所変更登記が義務化されます。この改正により、以下のルールが適用されます。
・住所や氏名に変更があった場合
変更から2年以内に住所変更登記を申請する必要があります。
・2026年(令和8年)4月1日より前に変更があった場合
過去の住所変更についても、変更登記をしていない場合は、2028年(令和10年)3月31日までに申請を完了しなければなりません。
このルールを守らないと、所有権を証明する手続きが複雑になる可能性があります。余裕を持って手続きを進めておくことをおすすめします。
41.飼い犬の登録変更手続き
ペットとして犬や指定動物を飼っている方は、引っ越し後に登録変更手続きを行いましょう。役所または保健所の窓口で申請して、「鑑札」を受け取ってください。自治体によっては、このほかに犬の登録料や注射済票交付手数料などの納付が必須となる場合があります。併せてご確認ください。
42.パスポートの手続き(本籍を変更した場合)
パスポートは、引っ越しで住所が変わっても、手続きや申請は不要です。住所を変更したいときは、所持人記入欄の旧住所を二重線で消して、手書きで修正します。このとき、修正液や修正テープは使わないように注意しましょう。
ただし、本籍地や氏名が変更になる場合は、手続きが必要になってきます。記載事項変更旅券を申請するか、変更後の住所や氏名でパスポートを新しく申請(訂正新規申請)するかのいずれかで、記載事項変更の手続きを行います。手続き方法の詳細は以下の記事で解説しています。
◆引っ越し時にパスポートの住所変更は必要?手続き必要なケースと申請方法を解説
43.通販サイト等の登録内容を変更
引っ越しで住所が変わった際、通販サイトなどに登録している住所を変更します。注文した商品が誤って旧居の住所に届かないように早めに手続きしましょう。
44.荷解き・ダンボールの片付け
梱包した荷物の荷解きを行います。引っ越し当日にやり残した荷解きを済ませて、新居で快適に暮らせる状態を作りましょう。荷解きが完了したら、ダンボールを片付けます。 ダンボールの処分方法として一般的なのは、自治体に回収してもらう方法です。ほかにも、引っ越し業者にダンボールを処理してもらう方法、ダンボール専用の回収箱に捨てる方法、古紙回収業者に回収してもらう方法、不用品回収業者に回収してもらう方法などがあります。自分のライフスタイルに合った処理方法を選択してください。
◆引っ越しの荷ほどきと片付けを、効率的に進めるコツを解説!
◆ダンボールの捨て方|引っ越しで使用した後はどう処理すればいい?
45.旧居敷金の精算
敷金とは、物件の損傷や賃料の滞納などによる貸主の損害を担保するために、契約者が賃貸物件を借りる際に支払うお金のことです。旧居の修繕などの原状回復にかかった費用と入居時に支払った敷金の差額を清算していくようになります。原状回復にかかった費用が敷金の金額内に収まっている場合には、残金が返却されます。旧居の退去後、部屋のクリーニングや補修を終えた段階で、管理する不動産会社や貸主から敷金の清算書が送られてきます。金額の内訳をよく確認し、費用に不明な点があれば不動産会社に確認をしてから清算しましょう。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越し後に必ずやることは?
引っ越しのときに、やることについて、よくある質問についてまとめました。
引っ越しの手続きはいつから始めればいい?
物件決定後すぐに着手が理想。役所やライフライン、工事が必要なネットは1~2か月前から前倒しが安全です。
引っ越し時、役所の手続きは何を優先すべき?
別市区町村へ移動する場合は転出届(旧住所側)→転入届(新住所側)。同市区町村なら転居届を14日以内に。
郵便の転送はどう申し込む?
郵便局で転居届を提出、またはe転居でオンライン申請。転送期間は1年間です。
引っ越しのとき、ライフラインはいつまでに?
電気・水道はオンラインで前倒し、ガスは立ち会い前提で日程調整。繁忙期は枠が埋まるため早めに。
不用品・家電の処分の注意点は?
家電リサイクル対象(エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビ)は自治体の粗大ごみでは出せません。また、引っ越しのときは、リサイクル料金と運搬費を確認しましょう。
自力引っ越しと業者、どちらが得?
自力引っ越しは費用をおさえられるメリットがありますが、破損や工数が増えるリスクがあります。荷物量、移動距離、人手、工数などで判断しましょう。
新居で電気や水が使えないときは?
電気はブレーカー、水は元栓・止水栓を確認しましょう。開栓の申請漏れの場合は、早めに各局へ連絡を。
不動産登記の住所変更は必須?
はい。2026年(令和8年)の4月1日から住所変更登記が義務化されます。また、変更から2年以内(経過措置あり)に申請が必要です。
郵送・オンラインだけで完了できる引っ越しの手続きは?
郵送・オンラインだけで完了できる引っ越しの手続きは、郵便転送、固定・携帯電話の住所変更、一括申請サービス経由の各種申請などが挙げられます。ただし、ガスの開栓は立ち会いが必要なため、オンラインのみでは完結しません。
引っ越しの手続き漏れを防ぐコツは?
時系列チェックリストと一括申請の併用。役所の用件は同日窓口でまとめて行うと効率的です。
引っ越しやることリストを使ってチェックしておこう!
今回は、引っ越し前から引っ越し後にやるべきことについて、基本的な情報をご紹介しました。引っ越しの大まかな流れを確認して、問題なく移住ができるよう準備しておきましょう。手続きに抜け漏れがあると、新生活に影響が出るおそれがあります。事前にチェックリストで確認し、着実に準備しておくと安心です。
これから引越しを控えている人は次の「引っ越しやることリスト」を利用しながら、スケジュールの管理に役立ててください。チェックリストをPDFとエクセルでダウンロードできます。
また、引っ越し関連の手続きをまとめて済ませられる、「引越れんらく帳」が役立ちます。
「引越れんらく帳」は、引っ越しの手続きを24時間いつでも、一度の入力で行うことができるサービスです。無料で登録でき、電気やガス、水道の手続きをまとめて出来ます。さらに、アラート機能も用意されています。引っ越しまでの日程に応じて、案内を受けられるので、手続き漏れを防ぐことができます。引っ越しの際には「引越れんらく帳」をぜひご利用ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

◆引っ越しの大まかな流れと当日の動き方とは?必要なものや注意点
◆【電気・ガス・水道の引っ越し手続き】ライフライン手続きの手順や注意点を解説
◆引っ越し手続きのやることチェックリスト!タイミングや必要書類などまとめて解説